腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸は腸管バリア機能と深い関りがあります!
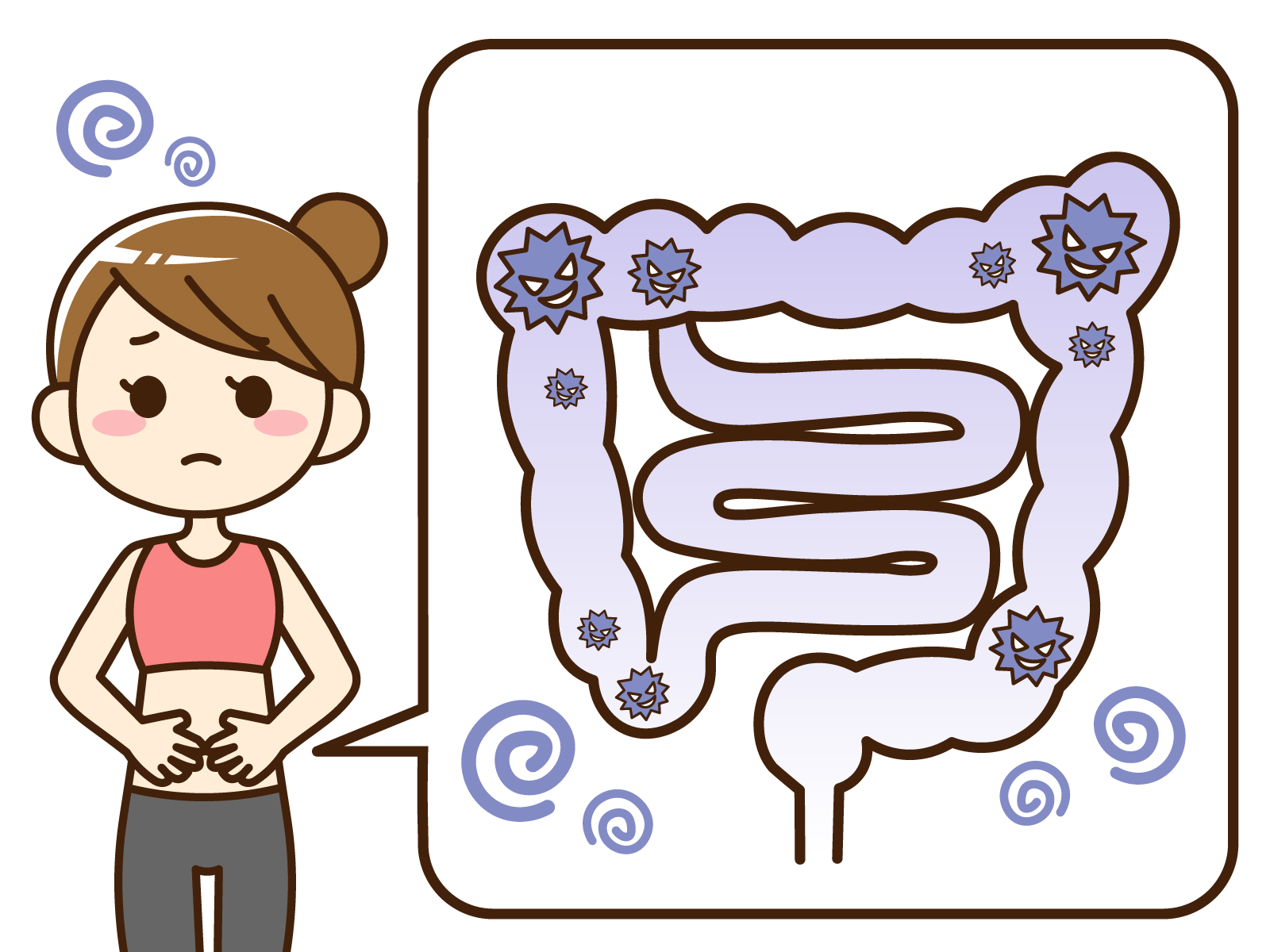
今日も引き続き、腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸の8つの有益な働きについてです。
今日は、④腸管のバリア機能を強化する、です。
ではまず、短鎖脂肪酸の働きの前に、腸管バリアとはどのようなものなのかについて触れたいと思います。画像は腸管バリアの働きが悪い不健康な腸のイメージイラストです。あまり深い意味はございません?!(笑)
食物を消化吸収する腸管には、食物抗原や細菌の毒素などが体内に侵入することを防ぐバリア機能が備わっています。以前のコラムでも腸管の表面を弱酸性に保ち、細菌やウィルスを防ぐ話しをしましたが、それらを含めたバリア機能のことを指します。
ちなみに食物抗原とは、食物に含まれ免疫系に認識されてIgE抗体の産生を誘導する物質(抗原)のことで、アレルゲンと呼ばれています。
腸管バリアはその構造と働き方により、大きく「物理的バリア」と「科学的バリア」の2種類に分けられます。この2つが組み合わさり、腸管の粘膜上皮では栄養素の消化吸収が行われ、腸管免疫にも深く関わっているのです。
まず、物理的バリアは、上皮層を覆う粘液と糖衣(糖鎖の集合体)、そして細胞間接着装置(タイトジャンクション)などのことを指しています。
続いて科学的バリアは、微生物に化学的な変化を与えて抗菌活性を発揮するもので、細菌の侵入を抑えるように働く数々の分子を指します。例えば、抗菌ペプチドやリゾチームを分泌することで粘膜表面を除菌しているなどです。
また、抗原を取り込み、粘膜固有層に存在する樹状細胞に提示し、免疫グロブリンA(IgA)が分泌されて病原体やアレルゲンの侵入を阻止して、病原体毒素を中和するように働いています。
これらが腸管バリアと呼ばれるものですが、短鎖脂肪酸が粘膜固有層における特定のIgA形質細胞の分化を促すことがわかっており、上記の化学的バリアにおいても重要な働きをしています。物理的バリアでは上皮細胞を形成するエネルギー源としての働きは昨日のコラムでも触れました。
このように、腸内細菌は代謝産物である短鎖脂肪酸を介して、腸管バリアの根幹である腸管上皮細胞を支え、間接的に腸管免疫と関わっていると言えます。

コメント