改めて、オメガ脂肪酸(3・6・9)を整理してみた!
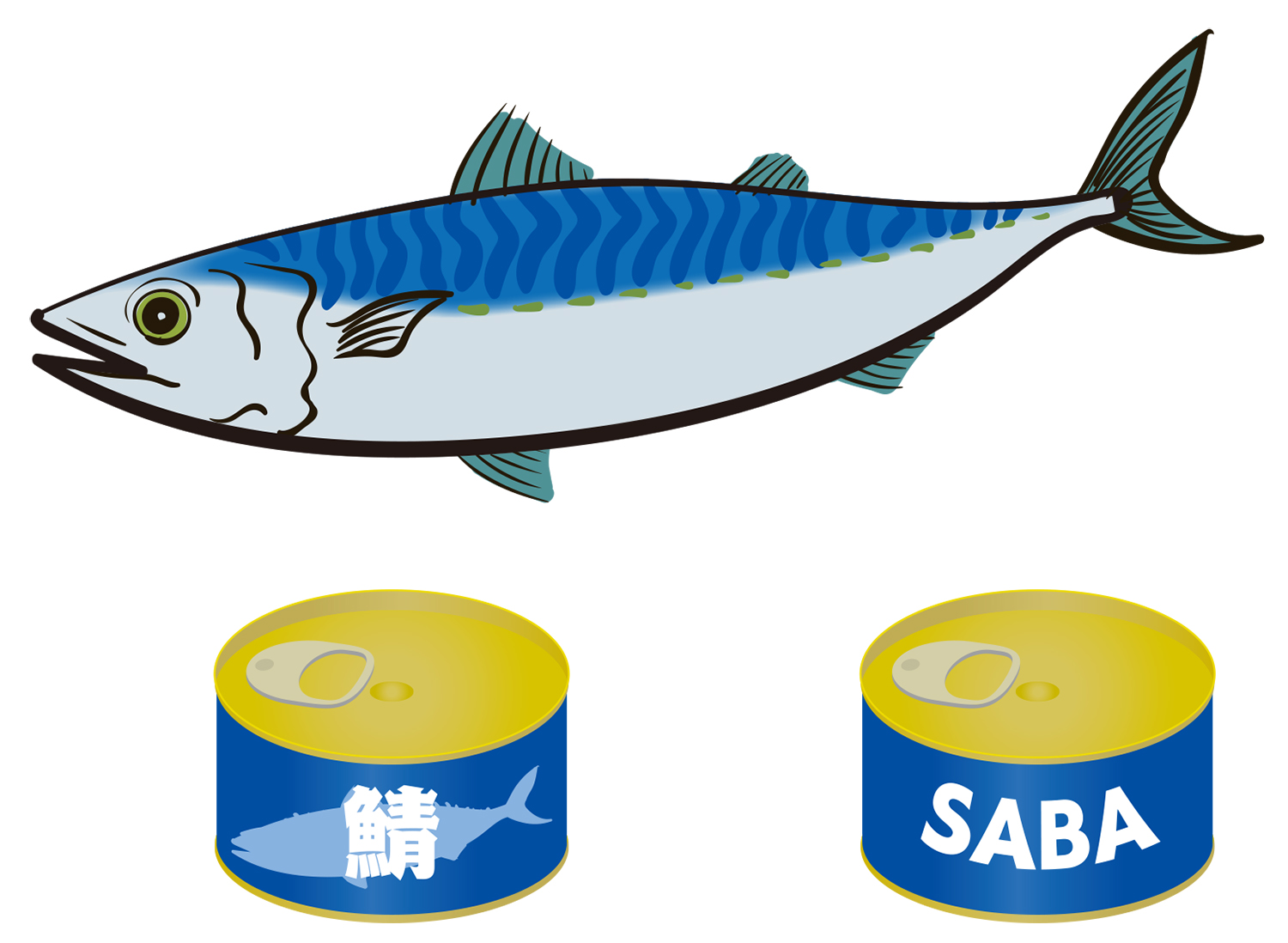
慢性炎症を防ぐ抗炎症作用のある食材をピックアップしていますが、3番目の食材としてオメガ3脂肪酸を含む食材を上げていました。
オメガ脂肪酸は3・6・9に分かれ、いずれも生きるためには必要な脂肪酸ですが、それぞれの摂取バランスが重要だと言うのが昨日までのコラムです(オメガ3とオメガ6は必須脂肪酸)。
今日は改めて、脂肪酸を不飽和脂肪酸と飽和脂肪酸に分けて整理したいと思います。
昨日も少し触れましたが、不飽和脂肪酸と飽和脂肪酸の1つ目の違いは、構造上の違いで、不飽和脂肪酸は炭素の二重結合があり、飽和脂肪酸には炭素の二重結合がないのが特徴です。
オメガ脂肪酸の3・6・9はいずれも不飽和脂肪酸ですが、炭素の二重結合が3番目、6番目、9番目に来ていることを意味しています。
常温での状態は不飽和脂肪酸は液体、飽和脂肪酸は固体です。
含まれる食材は、不飽和脂肪酸は青魚や植物性の油に対し、飽和脂肪酸は動物性の油になります。具体的には、不飽和脂肪酸がオリーブオイルや菜種油に対し、飽和脂肪酸はバターやラードになります。
これだけ見ると、なんとなくですが、不飽和脂肪酸の方が健康にいいように感じますね。
ここで、オメガ脂肪酸の3・6・9を見てみると、オメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸は多価不飽和脂肪酸(炭素間に二重結合が2個以上存在する)で、オメガ9脂肪酸は一価不飽和脂肪酸(炭素の二重結合が1つ)となり、代表的な脂肪酸は、オメガ3脂肪酸がα-リノレン酸、オメガ6脂肪酸がリノール酸、オメガ9脂肪酸がオレイン酸です。
そしてオメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸は体内で作ることが出来ず、食材から摂取する必要がありますが、オメガ9脂肪酸は体内で作ることもでき、食材から摂取することも出来ます。
食材としては、オメガ3が青魚、えごま油、亜麻仁油、オメガ6が、コーン油、大豆油、オメガ9がオリーブオイル、べに花油となります。
オメガ3、オメガ6の年齢別の摂取量なるものも農水省から発表されてはいますが、その分量を量って摂れるわけでもなく難しい話しになりますが、やはり青魚を積極的に摂取することでオメガ3脂肪酸の割合を増やしたいですね。
油はサラダ油より、えごま油、亜麻仁油と言いたいのですが、えごま油は熱に弱く酸化が早く使い勝手が悪い油ですから、菜種油が3・6・9のバランスが良く使いやすいとのこと。またオリーブオイルも必要に応じて適度に使うようにすればいいのではと思います。
オメガ脂肪酸は、体にとってとても重要な栄養素ですので、全体バランスを考えながら摂取していきたいですね。
明日は、オメガ脂肪酸を分子栄養学の視点から見ていきます。
画像は、青魚の代表選手、サバと鯖缶です!

コメント