この腸内細菌が棲息している人は、MCI(軽度認知障害)になりにくい!?果たしてその菌とは?
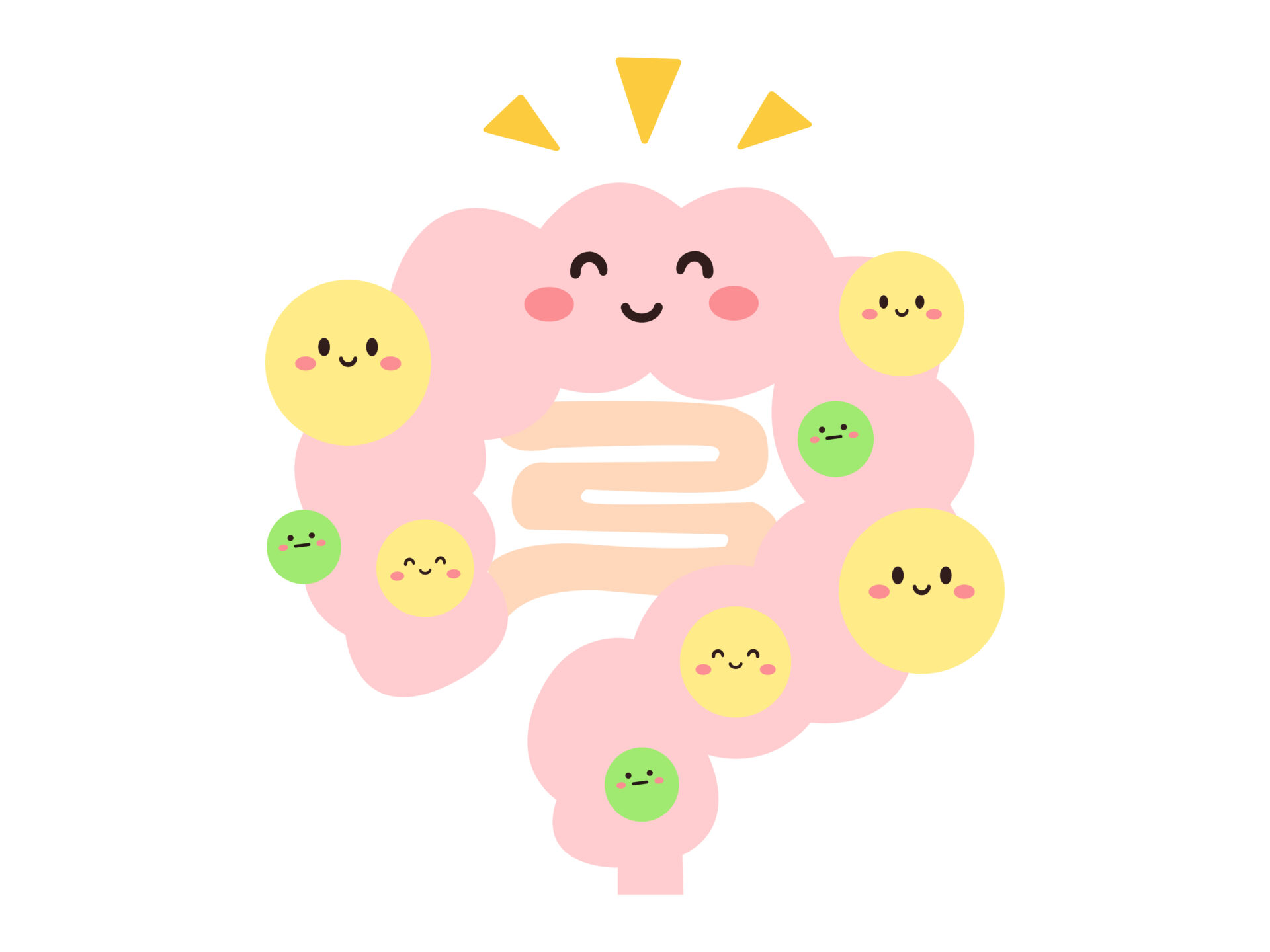
今日はMCI(軽度認知障害)についての最終回となります。昨日は脳腸相関とMCIとの関係性と、腸内細菌がMCIに与える影響についてお話ししました。
今日は、その影響を与える腸内細菌の中で、山元先生の講演の中でおっしゃっていた、ある特定の腸内細菌について見て行こうと思います。
オンラインで講習を受けている方が、そこまで腸内細菌に詳しくないと判断されてか、さらっと触れられていたのですが、この腸内細菌が多い人はMCIの割合が低いと言われた腸内細菌、それはズバリ、アッカーマンシア・ムシニフィラです。
アッカーマンシア・ムシニフィラは、このコラムでも何度か取り上げた腸内細菌です。
大腸の粘膜層に棲息する腸内細菌で、腸の粘液成分である「ムチン」を主な栄養源として利用し、腸内環境の健康維持に関わっています。
要するにムチンを分解したり、新しいムチンの分泌を促す菌とも言えます。
ムチン層が厚くなると糖分の吸収が減り、血糖値は下がります。逆に薄くなると血糖値が上がると言うメカニズムですが、アッカーマンシア・ムシニフィラを多く持つ人は、やせ型の方が多く、糖分調整が出来るため糖尿病にはかかりにくいとされています。
また、乳酸をほどよく消化しますので、乳酸が敵のマラソン選手にとっては、絶好の腸内細菌となります。
逆にアスリートに多い菌という所以はそういうところが作用しているのではと思います。
このアッカーマンシア・ムシニフィラの多い人がMCIの発症が少ないと言うのは、これらのメカニズムと深い関係があるのではと、私は想像します。
私たちの腸内細菌検査では、アッカーマンシア菌を有する人は、さほど多くはありません。たくさん棲息している人(構成比の10%前後)は、全体の1割にも満たないです。
ただ、やせ形で昔スポーツ、特に長距離をしていた人が多いのは確かです。昔とったきねずかでも、数十年後の現在においてもしっかり腸内細菌叢に残っているのが驚きでもあります。
構成比の10%前後を支配すると、そう簡単には変化しないんですね。腸内細菌おそるべしです。
検査を受けられた方の多くが、アッカーマンシア菌が欲しいと言われます。ただ言い換えれば、現在、棲息していなければ、新しく棲息させるのは難しいとも言えます。
あくまでも、MCIになりにくい菌が、アッカーマンシア・ムシニフィラだったと言うお話しでした。

コメント