免疫チェックポイント阻害剤で副作用が出ない要因に腸活は関係しているのか?
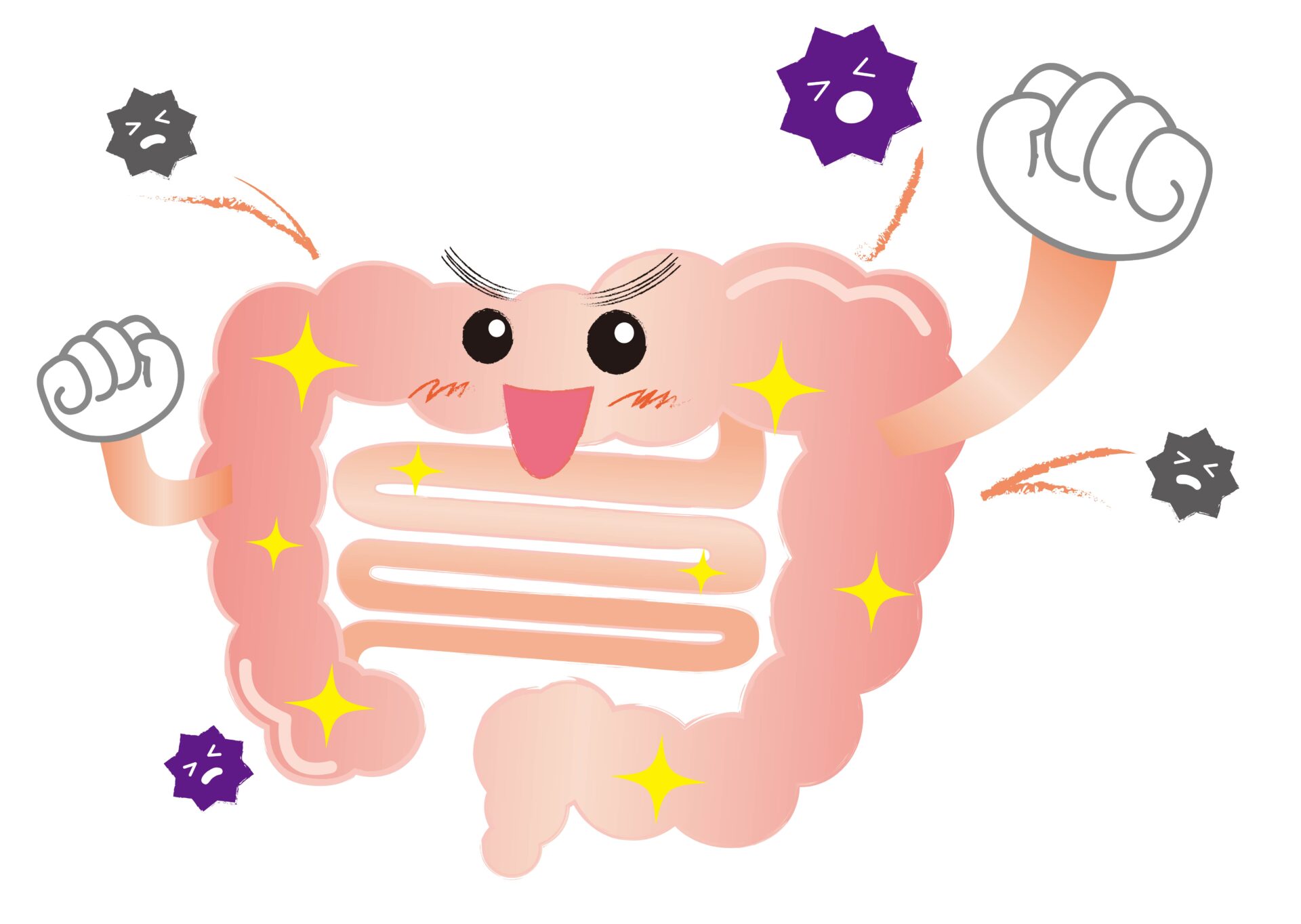
昨日のコラムの続きになりますが、肝臓の腫瘍マーカーAFPが、免疫チェックポイント阻害剤(テセントリク)と血管新生阻害剤(アバスチン)の5回の投与で正常値に戻った話しをいたしました。
本来なら副作用が出てもおかしくないところ、これと言った副作用がなく順調に回復しているのですが、その考えられる3つの要因のうち1つ目を昨日お伝えしました。
今日は2つ目の‟腸活”についてです。
母は昨年の夏、大腸がんの腹腔鏡手術を行い、S状結腸を10センチ切除いたしました。元々、大腸に棲む腸内細菌叢がどのようになっていたかを、腸内細菌検査で調べていれば良かったのですが、本人が検便を嫌がり、検査できずにいました。
よって腸活もしておらず、大腸がんを患うことになりました。
大腸がん手術の後、おそらくですが、大腸の腸内細菌はほぼ全滅状態?!であっただろうと推測できます。と言うのは、抗生物質は山のように投与されていますし、手術の際に大腸は思いっきり空気に触れているからです。
ただ逆に言い換えると、大腸がんの原因になったであろう悪玉菌も一掃されたとも言えます。
手術を経て、ある意味まっさらになった大腸に、どう腸内細菌を植え付けるかだけを考え、退院した日から腸活を始めました。
まずは、乳酸菌を積極的に摂取させ、ビフィズス菌は生きたまま腸まで届くものを摂取させました。特にまっさらの状態、すなわち赤ちゃんの大腸をイメージし、‟ミルミル”に含有されている赤ちゃんのビフィズス菌「ビフィドバクテリウム・ブレーベ」を摂取させました。
菌の代謝リレーを意識し、食物繊維から糖化菌、乳酸菌・ビフィズス菌、を意識したことは言うまでもありません。
術後に見られていた便秘は解消し、便の状態は良くなっていきました。
ちなみに、最近は2回、3回と通常便が出るようです。随分と腸内環境が良くなった証だと思います。
腸内細菌叢が整うと免疫チェックポイント阻害剤の効きが変わり、奏効率は10%以上上がります。この腸活が、癌細胞が消えるアシストをし、副作用を抑えている可能性はなくはないなと思います。
改めて健康は腸からだと思います。
明日は、3つ目の要因について触れていこうと思います。

コメント