腸内細菌が産出する酪酸が免疫機能を高めている以外に、DNAとの関りがあるってどういうこと?!
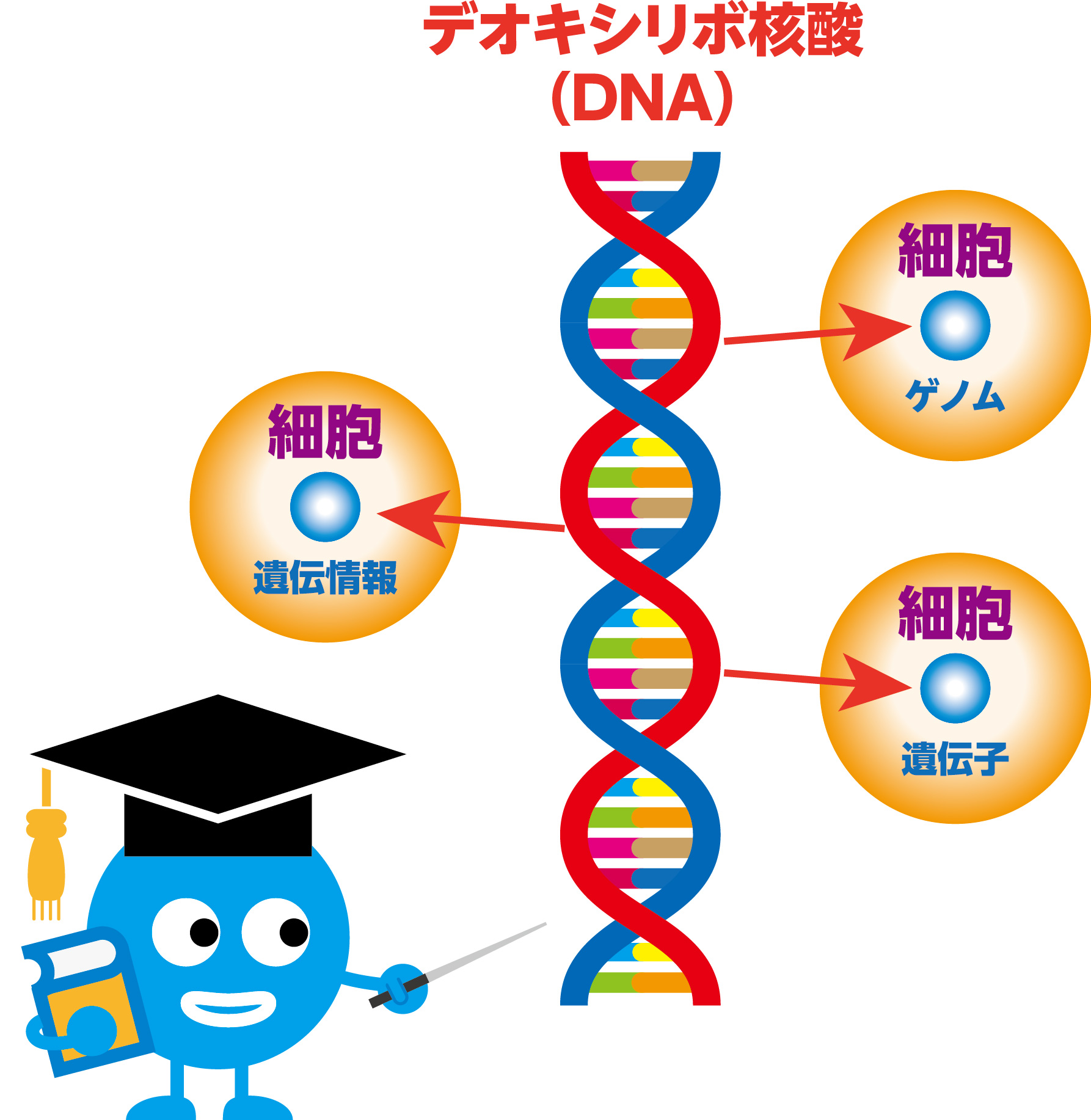
ここまでのコラムで、腸内細菌が産出する短鎖脂肪酸の酢酸とプロピオン酸について、それぞれの代謝部位や、生理的な役割について見てきました。
今日は、酪酸についてです。
画像は、DNA(デオキシリボ核酸)をイラストにしたものです。横の博士のような人物は私ではありません?!どうでもいいですね?!(笑)
本題は酪酸とDNAがどうつながるのかですね?
まず、酪酸は大腸上皮細胞のエネルギー源として利用されていて、全身循環に到達するのは約2%ほどです。しかし、その生理活性は非常に高く、①腸管バリア機能の維持や②抗炎症作用など免疫機能を高めています。
そして、③ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)の阻害によるエピジェネティックな遺伝子発現調節にも関与しています。
何やら難しい話しになりそうですね?!酪酸の役割で①②については、よく理解できるのですが、③はどういうことなのでしょうか?
エピジェネティックなという表現がありましたが、エピジェネティクスとは何かについて簡単に説明したいと思います。
エピジェネティクスとは、簡単に言うと遺伝子の塩基配列は同じなのに遺伝子の発現が変わる現象のことを言います。要するに、塩基配列以外の要因で遺伝子のオンとオフを決める仕組み、すなわち遺伝子に書かれた情報通りに従うか従わないかを選択する仕組みということになります。
遺伝子はDNAで記録されていて遺伝子情報が網羅されていますが、その遺伝子情報を使うか使わないかを決める機構がエピジェネティクスなのです。
例えば、DNAがきつくたたまれている(結合している)状態では、そこに書いてある情報を読むRNAポリメラーゼが入っていけないので転写することができません。これは遺伝子がオフの状態にあります。逆に緩くたたまれていればRNAポリメラーゼが遺伝子を転写することができます。こちらは遺伝子がオンの状態ということです。
具体的にはこの作用をヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)などの酵素が働いていますが、酪酸はHDACを阻害することで、遺伝子発現の調節機能を有効に働かせているのです。
ちょっとわかりにくかったかも知れませんので、短鎖脂肪酸からは少し話しがそれますが、このエピジェネティクスについて明日もう少し突っ込んでいきたいと思います。

コメント