<免疫チェックポイント阻害剤>造影剤CTの結果、腫瘍が当初の5%まで小さくなりました!
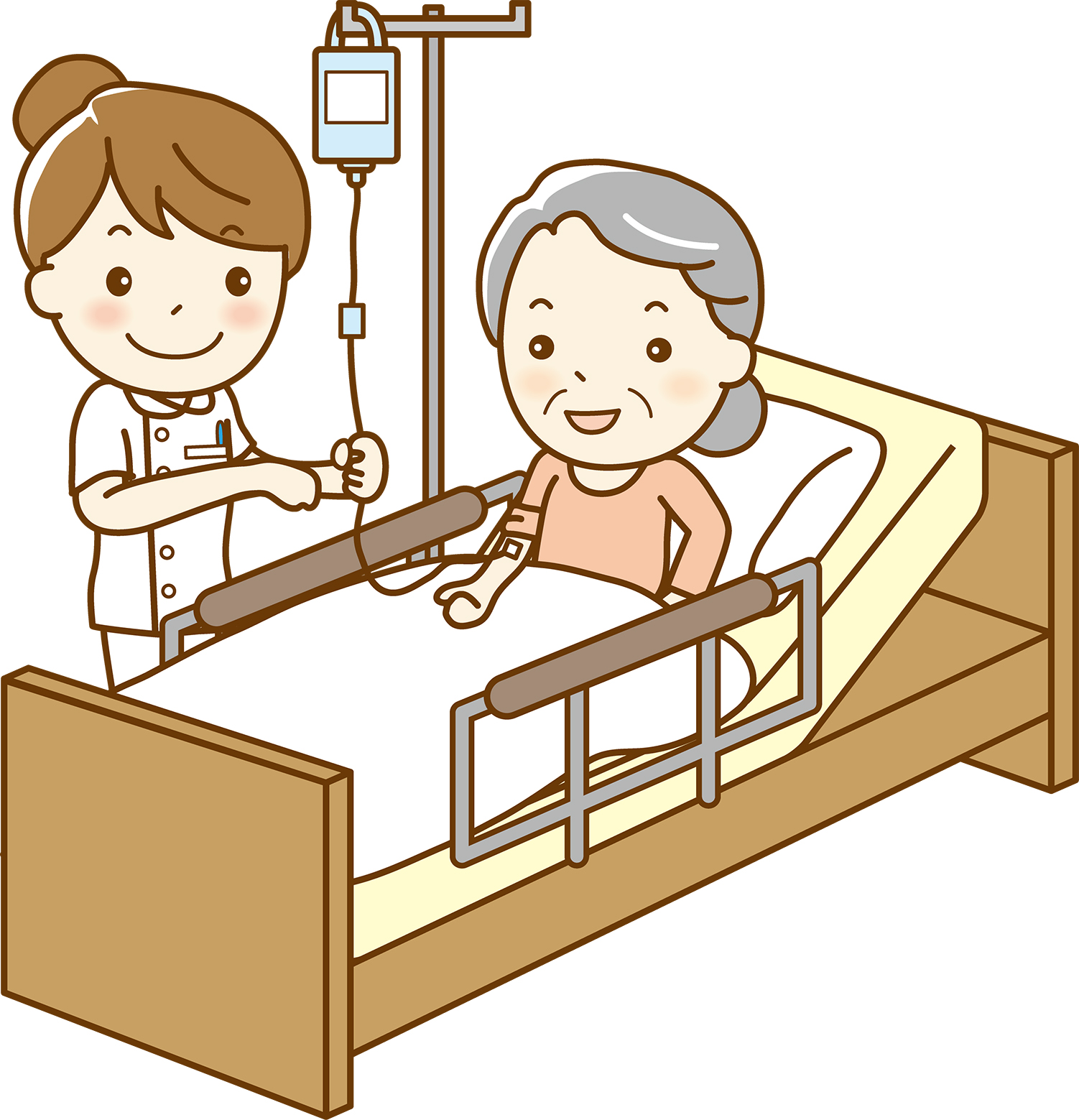
今日のコラムは、‟生きたまま腸まで届くビフィズス菌”から離れて、免疫チェックポイント阻害剤の治療経過です。
私の母が今年の5月末に肝細胞癌が見つかり、6月6日から免疫チェックポイント阻害剤(テセントリク)と血管新生阻害剤(アバスチン)の点滴を以後3週間ごとに続けていることは、これまでもお伝えしてきました。
今日8月29日が5回目の投与になったわけですが、これまで肝臓の腫瘍マーカーは、24400⇒7000⇒481⇒56と投与するたびに劇的に下がってきました。
腫瘍の状態を見極めるために、昨日、造影剤CTを行い、今日その検査結果が出ました。
腫瘍マーカーと腫瘍の大きさは基本的に正比例することが多いのですが、やはり腫瘍はこちらも劇的に小さくなっており、当初が100とすれば、現在は5%くらいまで縮小しておりました。
以前は門脈まで浸潤していた癌細胞もCTの画像を見る限り消えていました。
今回の治療で効果が出ているのですが、通常、免疫チェックポイント阻害剤で効果が出た方は、副作用も起きることが多いのですが、これと言う副作用は現在のところ出ておりません。
主治医の先生が同じ肝細胞癌の方で60代の方が、私の母と同じように腫瘍マーカーが下がり、いつのころからか正常値になり、1年後に腫瘍が小さくなったところで手術をしたら癌細胞が見つからなかったケースがあるとおっしゃっていました。
ただ、その方は副腎皮質ホルモンなどの副作用が併発したとおっしゃてました。
腫瘍が小さくなったところで手術をする意味は、手術した段階で抗がん治療(化学療法)を打ち切れるからです。
私の母の場合、高齢で副作用も見られないことから手術に踏み切ることはないと思いますが、どの段階で化学療法を打ち切るかが一つのポイントになりそうです。
では、なぜ副作用が見られないのかを明日考察していきたいと思います。

コメント