青魚を中医学の観点から見ると、栄養学的に見たEPAやDHAの効果と一致しているのか?
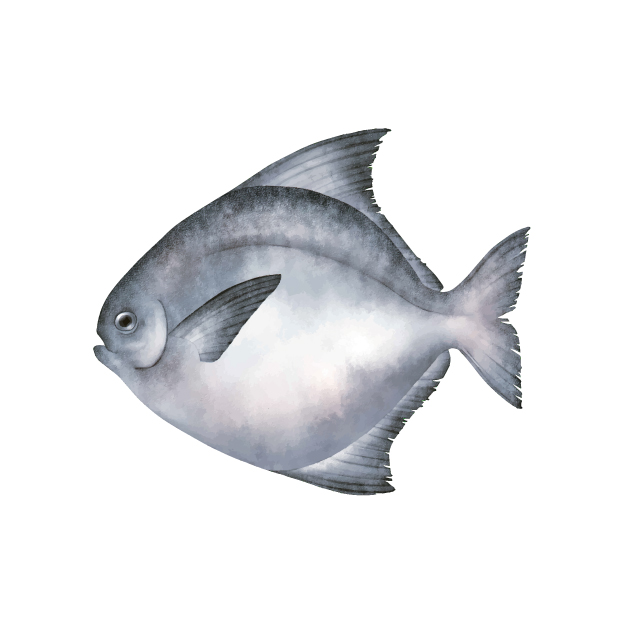
今日は中医学(東洋医学)の観点から青魚を見て行きます。
それぞれ青魚の種類ごとに効能は微妙に違うのですが、総じて言えるのは、補益気血であることです。いずれの青魚も気を補う、補気類に属し、同時に血(血液)も補います。
温性、もしくは平性が多く、体を温め気血の巡りを良くします。このあたりで、EPAやDHAの効能となんとなく近いことがわかります。
血の巡りを良くし、活血化瘀の性質もあることから、血瘀を防ぐまさに血液をサラサラにすることにつながっているとも言えます。
具体的に見ていくと、鰯(いわし)は温性で甘味の五気六味で補益気血の効能を有します。甘味は多くの青魚がその性味で、気血を補う性味とされています。
鮪(マグロ)は同じく温性で甘味、鰹(カツオ)や鯖(サバ)は平性で甘味の性味です。平性で涼性、寒性ではないため気血の流れを妨げるものではありません。
中でも鰯や鯖、鮪は帰経が肝で肝に入る(肝臓に効く)ため、より血を補い流れを良くする食材とも言えます。
ここで面白いのが、マナガツオです。鰹に似た、真名鰹(マナガツオ)と言われ、南日本から東シナ海に生息し瀬戸内海の浅瀬で産卵する青魚ですが、平性で甘味、益気養血の効能があります。
偽物の鰹とは言っても、本物の鰹よりも高い高級魚ですし、しっかり養血効果はあります。こちらもEPAやDHAがしっかり摂れる食材ですね。
中医学の観点でも青魚が栄養学として見たEPAやDHAを含有することと、概ね一致致しました。
いずれにしても、慢性炎症を防ぎ、抗炎症作用のあるEPAやDHAを含む青魚ですが、日替わりとまでは言わなくても、定期的に摂取したい食材であることは間違いないようです。
画像はマナガツオのイラストです。

コメント