PFCバランスにおいて、炭水化物を考える際には食物繊維は分けて考える必要があります!
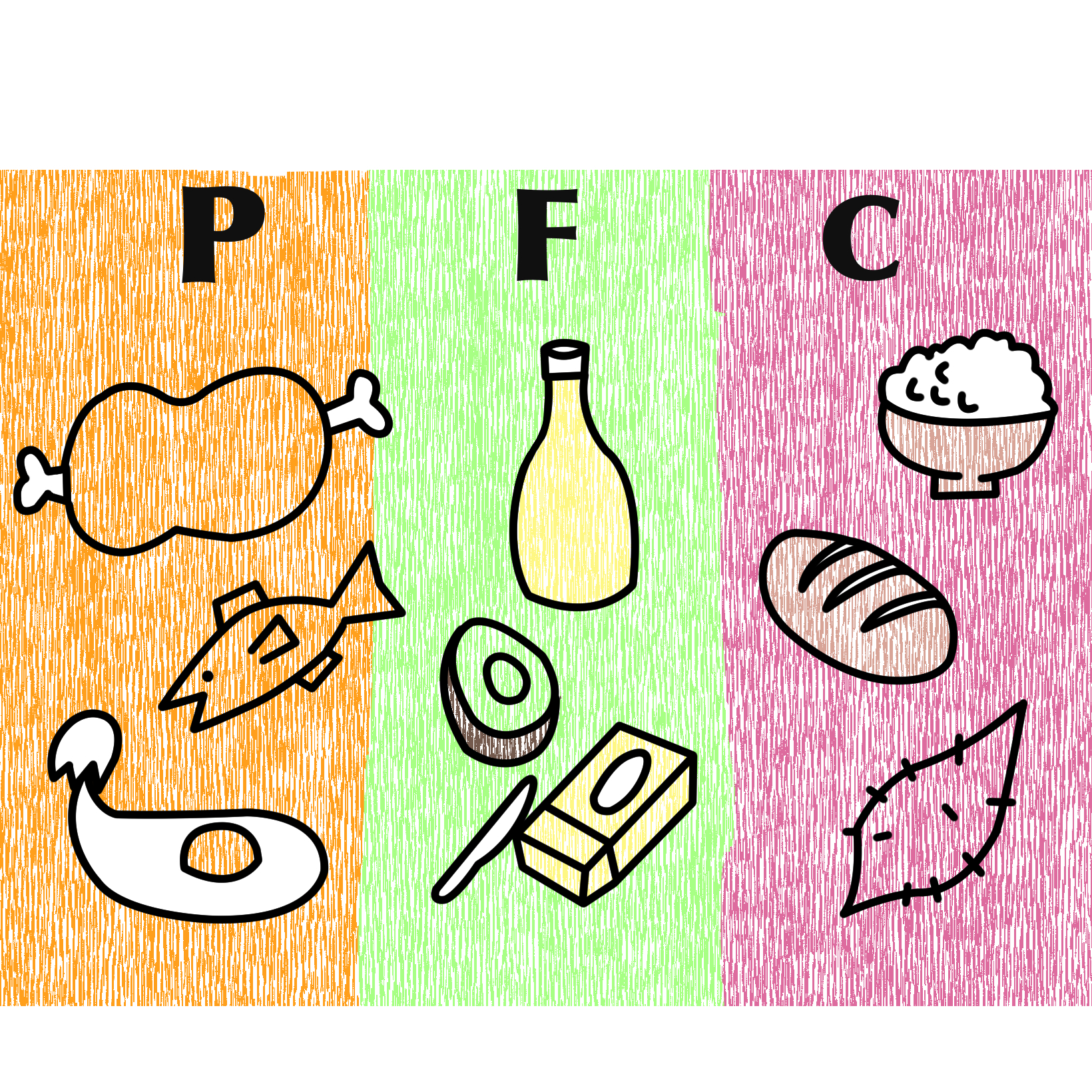
今日はPFCバランスの続きになります。画像は簡単なイメージイラストです。
昨日のコラムで、理想的な配分は18~49歳の男女の場合、たんぱく質が13~20%、脂質が20~30%(但し飽和脂肪酸は7%以下)、炭水化物は50~65%とお伝えしました。
これを摂取量で表すと、たんぱく質は65~100g、脂質は44~67g、炭水化物は250g~325g程度が1日の摂取量の目安になります。
ここで気を付けなければいけないのが、食物繊維についてです。
食物繊維は炭水化物に含まれているものの、人の消化酵素で分解することが出来ず、腸内細菌によってエサとなり最終的には短鎖脂肪酸等に代謝されます。
これは、食物繊維をエサにする麹菌や納豆菌などの糖化菌が乳糖などを生み、乳酸菌やビフィズス菌がその糖分を乳酸や酢酸に変え、それを酪酸菌が代謝して短鎖脂肪酸を生み出す、一連の菌の代謝リレーが行われることによります。
短鎖脂肪酸はエネルギー産生もしますが、0~2Kcal/gくらい微小で、腸管エネルギー産生に費やされると言われています。
短鎖脂肪酸がもたらす効果効能はエネルギー産生などを含め8つの有益な働きがあります。これらの詳しいコラムは、2024年1月18日をご覧いただければと思います。
話しを食物繊維に戻しますが、食物繊維は炭水化物に含められているものの、糖分として消化吸収されないため、まったく別に考える必要があります。
炭水化物のエネルギー産生は4Kcal/gですが、この数値は便宜的に食物繊維も含めているものですが、実際は食物繊維はほとんどエネルギー産生しないのです。
となると、炭水化物の1日の理想的な摂取量250g~325gも食物繊維は別に考慮する必要があると言うことです。
厚労省が発表している食物繊維の1日あたりの推奨摂取量は25g(2025年4月1日から)ですが、エネルギー産生にはこのグラム数は加算してはいけませんし、そもそも、腸内細菌は個人でかなりの構成比の差がありますので、一概に25ℊ推奨と言うのも疑問が生じます。
ここは自分自身の腸内細菌構成比を把握し、食物繊維をこなしてくれる腸内細菌がどれくらいいるのかを常にチェックしておくことが必要になります。
特に食物繊維を務めて食しているのに便秘気味と言う方は要注意です。腸内細菌が代謝できずにそのまま排出されるため、逆に便秘の原因になっているかも知れないからです。
このように、あくまでPFCバランスは一般的な人の平均値であり、その平均値から自分がどのくらい逸脱しているか、それは栄養素の消化吸収能力であったり腸内細菌構成比に照らす必要があると言うことになります。
そして、腸内細菌が与える影響は、想像以上に大きいと感じています。

コメント